指導:福山 透教授(薬学系研究科 薬科学専攻 天然物合成化学教室)
アルツハイマー病治療薬ドネペジル塩酸塩の合成に取り組んだ。生成物を抽出や再結晶、カラムクロマトグラフィーで精製し、MSやIR、NMRを用いて純粋なドネペジル塩酸塩を得たことを確認した。
非ステロイド性抗炎症薬インドメタシンの合成に取り組んだ。生成物をカラムクロマトグラフィーにより精製し、再結晶により、純粋なインドメタシンを得ることができた。
|
 |
|
指導:草加浩平教授(工学系研究科 機械工学専攻 設計工学研究室)
CADのソフトの「SOLID EDGE」を用いてストラップを設計し、RPを用いて設計したモデルを造形した。また、旋盤やドリルなどの機械を使って、首振りエンジンのピストン部分を機械加工した。
|
 |
|
指導:青山和浩教授(工学系研究科 システム創成学専攻)
システムダイナミクスを学習し、システム思考の重要性、有効性を理解した。システムダイナミクスのソフトを使い、それぞれ興味のある事象のシステムをモデル化し、シミュレーションを行った(テーマ:大気中のCO2量の変化,恐竜絶滅)。シミュレーション結果をもとに発表資料を作成し、研究内容のプレゼンを行った。
|
 |
|
指導:高橋 淳教授(工学系研究科 システム創成学専攻)
鵜沢 潔特任准教授(工学系研究科 システム創成学専攻)
CFRPとは、プラスティックの樹脂を炭素繊維に含浸させて成形することによって、その軽さを保ちつつ強度および剛性(変形しにくさ)を高めたものである。今回はそのCFRPについて学び、さらに成形演習を行った。
|
 |
|
指導:嶋田正和教授(総合文化研究科 広域科学専攻 広域システム科学系)
マメゾウムシ科昆虫は既に産卵された豆を忌避して産卵することで、豆ごとの卵の個数が均等になるように産卵することが知られている。アズキゾウムシ(Callosobruchus
chinensis)、ヨツモンマメゾウムシ(C. maculatus)の産卵分布行動を調べ、χ2適応度検定によって統計的に解析することで、実際にマメゾウムシが均等に産卵しているかを検証した。
オオツノコクヌストモドキ(Gnatocerus cornutus)の雄は闘争行動をとるが、一度負けた個体には「負け癖」がつくと言われている。闘争経験のないオオツノコクヌストモドキの雄同士を争わせ個体のサイズの勝敗への影響を探るとともに、その闘争に敗れた個体と新たな個体を争わせることで「負け癖」があるのかを統計解析を用いて検証した。
|
 |
|
指導:牛田多加志教授(医学系研究科 疾患生命工学センター 再生医療工学部門)
筋芽細胞は、分化して筋となる細胞である。分化前と分化後のマウスの筋芽細胞における分化調節遺伝子の発現の変化、物理刺激による分化中のこれらの遺伝子発現の変化をRT-PCR法により測定した.また,蛍光顕微鏡により、分化前後の筋芽細胞の形態変化を観察した。 |
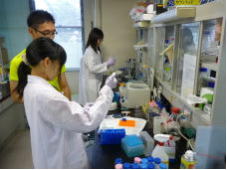 |